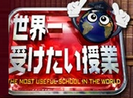8月下旬に開催された九州常歩会、非常に充実した内容になったのですが、そのなかで、私が再認識した内容が「遊脚が軸」という二軸のエッセンスです。
「遊脚が軸???そんなことありえない・・」という専門家の方も多いのですが、「遊脚が軸」という感覚(動き)が分かると、連続動作の理解が深まります。
私たちが「軸」という場合、ほとんど着地足をイメージしますね。
走歩行でも、サッカーのキックでも地面に接地している側の足を「軸足」と言ったり、イメージしたりします。
ところが、連続動作では身体の体制(姿勢)が動きを先取りする必要があるのです。つまり、走行動作において、左脚が着地して右脚が浮いている(遊脚)の時、すでに体幹(胴体)は遊脚側の右に重心をシフトする必要があるのです。
そうすることによって、素早い軸の切り替えができます。
先日の講習会に、熊本からS級の競輪選手が参加されていました。彼が、自転車のペダリングと体幹の移動(重心の位置)についての説明をしてくれました。彼によれば、普通の人(一般の人々)は、ペダルを踏みこむ(下がる)側に重心を移動させていくそうです。
しかし、S級の競輪選手は逆で、ペダルと踏み込む側と逆側、つまり上支点に向かう脚側に重心がシフトしていくそうです。(写真は山内卓也選手・愛知県・S級一班)
走りで言えば、まさしく遊脚側に重心がシフトしていきます。つまり、遊脚側が軸となるのです。
この動き、体幹を垂直に保つことが大切です。この動きは股関節の可動域と大きな関連があるようです。