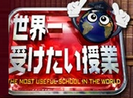身体の部分を使って、状態や感情・気持ちなどを表現することがあります。例えば「頭がきれる」「肩を落とす」「腹がたつ」などなど。「身ことば」とか「からだことば」などと言うようです。
その「からだことば」の中に、「あごを出す(上がる・上げる)」という表現があります。
この意味は何でしょうか。今週は、会う方々に、その意味を聞いてみました。若い方の中には、知らない方もおられましたが、ほとんどの方は知っています。
「あごを出す(上がる・上げる)とは、日本では「あきらめる」とか「仕事を途中で投げ出す」または「疲れた」状態をあらわします。
ところが、英語では逆の意味になるようです。
「Keep your chin up ! (あごを上げろ、出せ)」は、「しっかりせよ」とか「仕事にとりかかれ」「がんばれ」といった意味になります。あごを出すという「身ことば」が、東西ではほぼ逆の意味にになるようです。
私の知り合いに、米軍の海兵隊員がいます。海兵隊の「アテンション=気をつけ」の姿勢は、「あごをすこし出して、お尻を後ろに引け」と指導するらしいのです。
日本の「気をつけ」は、「あごを引け〜〜」といいますね。
「あごを引く」日本文化と「あごを出す(上げる)」西欧文化、とてもおもしろいです。

しかし、さらに興味深いのは、日本でも動作に適した姿勢は「あごを出す」ことだとする史料が散見されることです。
宮本武蔵の「五輪書」には「おとがいを出す」という表現があります。「おとがい」とはあごのことです。
また、戦前の軍事教科書にはあごを引いた「気をつけ」の姿勢ではなく、海兵隊の「気をつけ」姿勢に近い「不動の姿勢」が紹介されています。