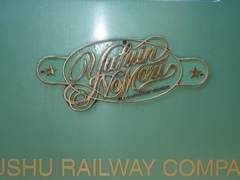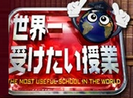ザックジャパンが韓国に圧勝した。札幌ドームで10日開催されたサッカーのキリンチャレンジカップで日本は韓国を3―0で制した。試合は前半35分、香川選手が相手DFをかわして右足でゴール。日本が球を支配しシュートを連打する中での先制点。後半には本田選手、再び香川選手がゴール。
所用により帰りが遅く、ニュースでゴールシーンのみを拝見したが、香川選手の細かいステップは圧巻。現時点での日本代表ではその動きは群を抜いている感がある。そして、後半、本田選手と香川選手のゴールををアシストした選手の動きに目を奪われた。冷静な判断力、そしてピンポイントで合わせる技術。ご本人には申し訳けないが、昨日まで知らなかった。C大阪の清武弘嗣選手(21歳)。同チームでは、昨年のW杯前までは控え選手だったらしい。香川選手や家長選手の海外移籍でスタメンを獲得。今回、はじめてA代表に招集された。 メンバー発表まで、まさかA代表に選出されるとは本人も思っていなかったとのこと。
日本代表の多くが海外でプレーする時代となった。海外のトップ選手とプレイすることで無意識に技術は伝達される。トップレベルの技術や技は、意識から意識へ伝達されるのではなく、「無」から「無」へ受け継がれるものだ。 昨日の日韓戦を見るかぎり、なでしこに続き、男子サッカーがW杯を獲得することも決して夢ではないと思えてくる。