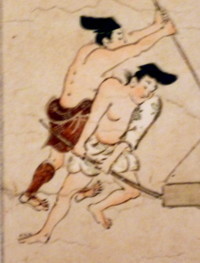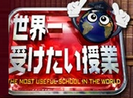先日、「スポーツ大会なのに・・」の記事をを掲載しましたが、タイミングよく囲碁がアジア大会の正式種目に採用された報道がありました。
中国・広州で今年11月に開催されるスポーツの第16回アジア競技大会(アジア大会)で、囲碁が正式種目になりました。日本の棋士が初めて本格的なスポーツ大会に出場することになります。
今回、囲碁は開催国・中国の意向で採用されました。すでに正式種目になっていたチェス競技枠の中に、囲碁、チェス、中国将棋(象棋〈シャンチー〉)の3ゲームが行なわれます。
選手派遣には日本オリンピック委員会(JOC)への加盟が必要で、日本棋院と関西棋院、日本ペア碁協会の国内3団体が加盟へ向けた統一組織づくりを急いでいます。
大会では、団体戦の男子(5人制)と女子(3人制)、男女が交互に打つ混合ダブルス(ペア戦)の3種目が行われます。それにしてもダブルスの囲碁とはイメージがわきません。
囲碁は日本では文化と位置づけられることが多いが、国際的には「頭脳スポーツ」という言葉も定着しつつあるらしい。また、今回出場する棋士は陸上選手などと同様、ドーピング検査を受けることになります。
日本選手・・この表現もイメージがわかない(笑)・・の健闘を祈念しましょう。