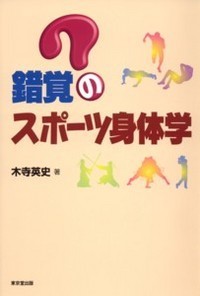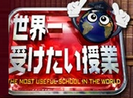先日(平成24年10月14日)、「ジャパンライム」よりご依頼を受けておりました常歩(なみあし)剣道のDVD撮影を行いました。午前9時に開始した撮影も、ほぼ予定通り16時には終了。スタッフの皆様、学生諸君、またご協力いただきました方々、ありがとうございました。
常歩(なみあし)による剣道は、古流や日本刀の操作(刀法)に戻るのではなく、「しない」の操作の合理性を求めて構築してきました。現代剣道(しない打ち剣道)への批判は「刀法から離れている」というものがほとんどです。ですから、多くの場合、古流や「刀法」に回帰することを求めています。しかし、私は逆に「刀法」を捨て「しない操作の合理性」を追求しようと考えてきました。すると、先日の「しないと日本刀」の記事にも記したように、多くの古流実践者の皆様から自流に酷似しているとのお話をうかがいました。
つまり、「しない」を「しない」として独立させた方が、本来の「刀法」に近づくことができるのです。「日本刀」を捨てると「チャンバラ」のように剣道の型が崩れるとイメージする方が多いまもしれませんが、そうはなりません。なぜなら、「しない操作」に「日本刀」から受け継いだ技術の経過性が含まれているからです。構え・攻め・打突・残心という一連の経過を「刀法」の客観的な技(動作)としてでなく、「しない操作」の合理性の中にある「運動経過」として包含することができるからです。つまり、相手をどのように打突するか、という技術の経過性こそ「剣道らしさ」の源であり将来に向けて大切にしなければならないものだと考えます。
本年中には、DVDが発売される予定です。様々な分野の方々にご覧いただきたい内容にしました。是非ご覧ください。